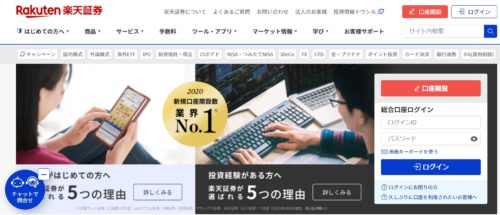色々な本や動画を読み、人に話を聞いている中で感じた資産運用について、出来るだけ失敗しない方法を探してみました。その結果、自分なりに決めたルールを備忘録として残そうと思います。
結果報告も随時していきますね。よかったらご覧ください。
資産運用のルールを決める
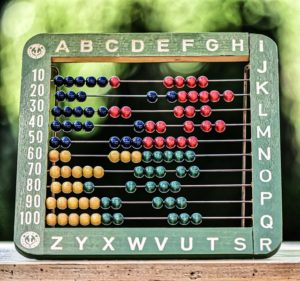
元本が保証されない、損をするリスクのある世界。
そんな資産運用の中で、将来がわからないなら、せめて投資のルールを決めて、損をした時にどうすべきだったかを考えれる流れにしたいと思いました。
投資を行う目的、時間と金額を決める
目的と失ってもいい時間と金を決めます。
今回は65歳以降の老後資金確保を目的としている分です。
私の場合、色々無駄に悩むタイプなので、月に2時間、月1万円からスタートしました。
長期運用か短期運用か

毎日の値動きにハラハラしていては、儲かったとしても、時間や精神的に失うものが多い。
そのため、1年以上の保有を前提に動きたいと思います。
長期運用のデメリット
調べている感じでは、長期運用では値下がりしても損切りができず塩漬け状態になるとのこと。
買う時のルール
もっと安く買えるかもと思えば、いつまでも買えません。
そのため、毎月1万円を買い続ける形としてました。「ドル・コスト平均法」という考えを参考にしました。平均的に変えれば、高すぎる金額では買うことはなさそうです。(ただ、この方法だと売買手数料は多くかかるので証券会社選びが重要となりそうです)
ドル・コスト平均法(英: dollar cost averaging、DCA)とは、株式や投資信託などの金融商品の投資手法の一つ。定額購入法ともいう。金融商品を購入する場合、一度に購入せず、資金を分割して均等額ずつ定期的に継続して投資する。例えば「予定資金を12分割して、月末ごとに資金の1/12を投入し、一年かけて全量を買う」という手法。USドル建てで投資することを意味するものではない。
高値掴みのリスクを避けるための時間分散の一種であるが、数量を等分するのではなく、金額を等分する点が単なる分散と異なる。価格が高い時は購入数量が少なく、安い時には多いため、単純な数量分割に比べ平均値の点で有利になるとされる。ただし価格が下がった場合のみならず、上がったときにも買う点で難平買いとは異なる。
長期投資でリスクを抑制し、安定した収益を得たい場合に使われる手法である。上げ相場でドル・コスト平均法を行うと(最初に一括で購入した場合と比べて)平均購入単価がかえって高くなり、収益を減少させてしまう欠点もある。タイミングを精密に測れないため、値動きの激しい商品で、ハイリターンを目指す投資には向かない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
売る時のルール
もっと高く売れるかもと思えば、いつまでも売れません。
ただ、65歳までの資産形成が目的なので、まずは1年間はうりません。
購入対象のルール
これまた、商品の数が多く悩みそうです。
でも長期運用を決めたので、リスク分散のため、次を軸に動こうと思います。
2種類以上の異なる商品を買う。ただし、年間値動き幅が、上下で30%以上のものは買わない。
2か国以上の国の商品を買う。ただし、金融システムが安定していない国のは買わない
ほったらかしにしないルール

毎月1回の購入時に、値段が5割を切ってないかぐらいはチェックしようと思います。
資産運用の目標に幅を持たせる
65歳までの資産形成を目的としていても、スタートから数年は勉強期間と考えています。気長にいかないと、何のためにしているのか分からなくなりそうです。